| 保険には、死亡保証目的、様々なリスク保証目的、節税目的等があるため、取扱も複雑です。そこで、保険と税金との関係で質問の多い点をQ&A方式で整理してみます。
Q.
会社契約で生命保険に加入する予定です。被保険者は社長(50歳)で、保険期間を80歳までとした場合、全額損金となりますか。
A.
質問のケースでは、保険期間満了時の被保険者の年齢は80歳であり、70歳を超えています。このような場合には、『長期平準定期保険』の可能性を考える必要があります。
長期平準定期保険とは、定期保険のうち、特に保険期間が長いものをいい、具体的には、保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、加入時の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるものは、税務上、長期平準定期保険として取り扱われます。
長期平準定期保険の税務処理は、保険期間の前半の6割の期間は、支払保険料の2分の1を前払保険料として資産計上し、残りの2分の1は損金に算入します。後半の4割の期間は、保険料全額を損金に算入するとともに、前半6割の期間で資産計上した前払い保険料をその期間に応じて取り崩して損金に算入しますので、前半6割と後半4割では、損金算入可能額が大きく変わります。
この仕組みの趣旨は、図表1のように、本来の死亡率から想定される自然保険料と平準保険料の差額は保険料の前払いであり、長期平準定期保険の場合、保険期間の中途で解約したときに多額の解約返戻金を受け取るケースがあるのを無視できないことによるようです。
質問のケースの判定と処理は図表2のように、結果は図表3のようになります。
図表1
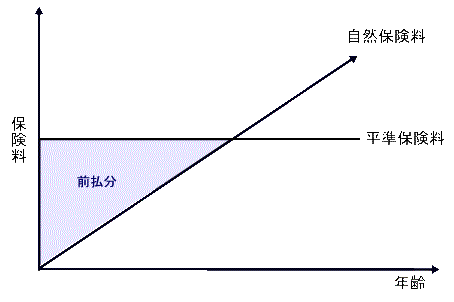
図表2
1.判定
①80歳>70歳
②50+(80-50)×2=110>105
※長期平準定期保険に当たる。
2.年払保険料が200万円とした場合の処理
(1)保険期間の前半6割の期間(18年間)の処理
保険料の2分の1を保険料、残りを前払保険料として次の仕訳を行ないます。
|
借方 |
貸方 |
|
支払保険料
前払保険料 |
100万円
100万円 |
現金・預金
|
200万円
|
(2)保険期間の後半4割の期間(12年間)の処理
保険料の金額と、それまで前払保険料としてきた金額(100万円×18年=1,800万円)を残りの期間で均等に按分(1,800万円÷12=150万円)して取り崩して損金に算入します。仕訳で示すと次のようになります。
|
借方 |
貸方 |
|
支払保険料
|
350万円
|
現金 ・ 預金
前払保険料 |
200万円
150万円 |
図表3
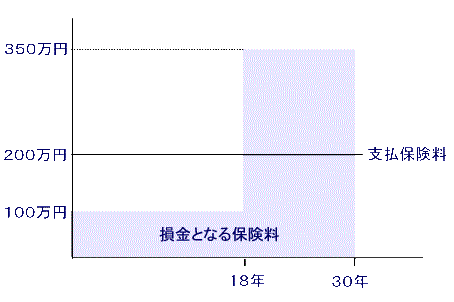
Q.
生命保険契約に関する評価方法が変更されたそうですが、具体的にどう変わったのですか。
A.
生命保険契約に関する権利の評価の経過措置を講じたうえ廃止し、解約返戻金の額を用いて評価することになります。
(1)従来の取扱い
生命保険契約でその契約に関する権利を取得したときに保険事故が発生していないものに関する権利の価額は、相続税法において、下の算式で評価するものとされていました。
ただし、保険料を一時払いした場合には、払込保険料の全額で評価されます。算式によれば、例えば解約返戻金が支払い保険料の合計とわかっていても評価額は70%以下になり、不合理に税負担が軽くなるということで改正されたようです。
(2)経過措置
実務上の慣行もあるため、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの3年間に相続または遺贈により取得した生命保険契約に関する権利については、引き続き従来の取扱を認めています。
Q.
所得税の計算において保険期間が10年以上ある損害保険があるので、長期損害保険として処理したら訂正させられました。なぜですか。
A.
損害保険料控除として所得控除の対象となる金額は、次の図表4のとおりです。
特に、長期損害保険は、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金のある損害保険契約であるという条件があり、間違いやすいので注してください。
図表4 所得税の損害保険料控除
①.保険期間が10年以上で満期返戻金のある損害保険契約(長期損害保険)
|
1年間に支払った損害保険料の金額 |
損害保険料控除額 |
|
|
10,000円以下 |
支払保険料の全額
|
|
10,000円超 |
20,000円以下 |
(支払保険料×1/2)+5,000円 |
|
20,000円超 |
|
一律15,000円 |
②.その他の損害保険契約(短期損害保険)
|
1年間に支払った損害保険料の金額 |
損害保険料控除額 |
|
|
2,000円以下 |
支払保険料の全額
|
|
2,000円超 |
4,000円以下 |
(支払保険料×1/2)+1,000円 |
|
4,000円超 |
|
一律3,000円 |
③.①と②の両方の契約がある場合
長期損害保険について①により計算した金額と短期損害保険について②により計算した金額の合計額となりますが、限度額は15,000円になります。
|
![]()