税理士、総務、申告、愛知県・名古屋市を拠点に経験豊かな税理士が税務、会計など会社経営の問題解決をお手伝いします。
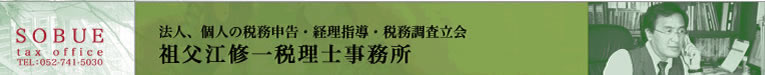 |

| ■改正された減価償却制度--19年7月号 -2007年6月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
7月の税務と労務 国 税 6月分源泉所得税の納付 7月10日 国 税 納期の特例を受けた源泉所得税(1月〜6月) 7月10日 国 税 所得税予定納税額の減額承認申請 7月17日 国 税 所得税予定納税額の納付 7月31日 国 税 5月決算法人の確定申告(法人税・消費税) 7月31日 国 税 11月決算法人の中間申告 7月31日 国 税 8月、11月、2月決算法人の消費税の 中間申告(年3回の場合) 7月31日 地方税 固定資産税(都市計画税)第2期分の納付 市町村の条例で定める日 労 務 社会保険の報酬月額算定基礎届 7月10日 労 務 障害者・高齢者・外国人雇用状況報告 (100人以上の事業場) 7月17日 労 務 労働者死傷病報告(4月〜6月分) 7月31日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ワンポイント 中小企業の資本金 中小企業法では中小企業を、資本金・従業員規模により、サービス業は5,000万円以下又は50人以下などと定義していますが、税法上の範囲は異なり、特定同族会社の留保金額の適用除外規定や法人税の軽減税率では、対象となる中小企業を資本金1億円以下としています。 改正された減価償却制度のポイント 平成19年度税制改正により、平成19年4月1日以降に取得をする資産から、減価償却に関する取扱いが大きく変わっています。 具体的には、今まで重要な計算要素であった残存価額と償却可能限度額が廃止となり、法定耐用年数内において取得価額を全額(備忘価額として1円は残す)償却することが可能になりました。 この改正の趣旨は、国際比較すると不利になっていた制度を改め若干有利にして、企業の新規設備への投資を促進し、国際競争力の強化、日本経済の持続的成長を意図したものです。 以下、ポイントを具体例を用いて説明します。 1.概要 (1)残存価額の廃止 平成19年4月1日以降後に取得をする減価償却資産について、残存価額が廃止されます。 そうなると、定額法や定率法の計算においては、残存価額を考慮しません。定率法においては、残存価額が算出されない仕組みのため、250%定率法(定額法の償却率×2..5倍の償却率)とそれています。 (2)償却可能限度額の廃止 平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、償却限度額を廃止し、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できるようになりました。 定率法採用している場合には、定率法により計算した減価償却費が一定の金額を下回るときに、償却方法を定率法から定額法に切り替えて減価償却費を計算することになります。これは250%定率法をずっと採用していると、耐用年数経過時点で償却完了がしないからです。 (3)平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産 従来よりの旧定額法・旧定率法により計算し、償却可能限度額(取得価額の95%)まて゜償却した事業年度の翌事業年度以降、5年間で均等償却できる(備忘価額1円は残す)こととされています。 2.前記において償却可能限度額まで償却済みのケース 平成19年3月31日までに取得した減価償却資産については、従来の減価償却の方法(旧定率法又は旧定額法)で減価償却を行い、償却可能限度額(取得価額の5%)に達した事業年度の翌事業年度以後5年間で均等償却することが出来ます。 3.平成19年度4月1日以後取得する減価償却資産(定額法) 残存価額、償却可能限度額がなくなります。 4.平成19年度4月1日以後取得する減価償却資産(定率法) 定率法の償却率が下の図表に示されているように定額法の2.5倍となり、耐用年数で,耐用年数で償却させるために中途で定率法から定額法への変更が行われてます。 なお、この償却方法の変更時点の目安がわかるように図表に示した減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表10では、保証率というものを公表しており、定率法による償却費が取得価額にこの保証率を掛けた金額未満になったら、定額法を用いることがわかるようになっています。 図表 新設された別表10
信用取引による所得の帰属時期 本年初めて、株式の信用取引により空売りを行いました。これについては翌年になってから反対売買により決済したいと考えておりますが、このような信用取引から生ずる所得は、いつの年分の所得として取り扱われるのでしょうか? 信用取引により売付けを行った株式については、実質的には、反対売買による決済を行うまでは譲渡原価が確定しないため、取引が完了していないと解されます。 したがって、税務上も、信用取引による株式の売買から生ずる所得は、その信用取引の決済の日の属する年分の所得とそれます。 ちなみに法人が信用取引による株式の売買を行った場合も、個人が行った場合と同様に考え、信用取引の決済の日の属する事業年度で収益を計上します。この際の株式の譲渡原価は、一般の株式の帳簿価額とは区分して計算されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税務だよりー一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||