�ŗ��m�A�����A�\���A���m���E���É��s�����_�Ɍo���L���Ȑŗ��m���Ŗ��A��v�Ȃlj�Ќo�c�̖�����������`�����܂��B
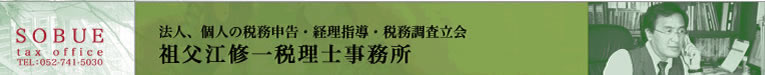 |

| �����z�������p���Y---�P�W�N�U�����@-2006�N6��5���@ | |
 |
�U���̐Ŗ��ƘJ�� ���@�� �T���������ł̂̔[�t�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�U���P�Q�� ���@�� �����ł̗\��[�Ŋz�̒ʒm �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�U���P�T�� ���@�� �S�����Z�@�l�̊m��\���@�@(�@�l�ŁE����œ�)�@�@�@ �@�@�U���R�O�� ���@�� �P�O�����Z�@�l�̒��Ԑ\���@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�U���R�O�� ���@�� �V���A�P�O���A�P�����Z�@�l�̏���œ��̒��Ԑ\�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�N�R��̏ꍇ)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�U���R�O�� �n���� �l�̓s���{�����ŋy�юs�������ł̔[�t �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(��P����)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@�s�����̏��Œ�߂�� �J�@���@���N�ی��E�����N���ی��ܗ^���x���́@�@ �@�@�@�@�x����T���ȓ� �J�@���@�����蓖������(�s��������ɒ�o) �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�U���R�O�� |
|
�����|�C���g�@�@�@�������x�̔p�~ �@�@�@�@�@ �@�������x�́A��O�҂̊Ď��ɂ�錡���I���ʂ�ړI�Ƃ��āA���z�ȏ�̏������z���͐Ŋz������ꍇ�ɁA�Ŗ����̌f���ɁA����(�Ж�)�A�Z���A�������z�����������鐧�x�B�{�N�S���P������A�����ŁA�����ŁA���^�ŁA�@�l�ŋy�ђn����(���ݓK�p��~��)�̐\�����ɌW��������x���A�p�~����Ă��܂��B 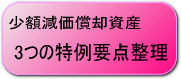 �@�F�\�������o���钆����Ǝғ����A�R�O���~�����̌������p���Y���擾�����ꍇ�ɁA�S�z���Z���ł������x���A�����P�W�N�x�Ő������ŏ���K������邱�ƂɂȂ�܂����B���f�������Ӗ��ňȉ��A���z�������p���Y�Ɋւ���R�̃|�C���g��������܂��B 1.�T�v �@�@�l�����Ƃ̗p�ɋ������������p���Y�ŁA�g�p�\���Ԃ��P�N�����ł�����̖��͎擾���z���P�O���~�����ł�����̂ɂ��ẮA�����o���ɂ�葦�������Z���ł��܂��B 2.�擾���z�̔��� �@�擾���z���P�O���~�����ł��邩�ǂ����́A�ʏ�P�P�ʂƂ��Ď������邻�̒P�ʁA�Ⴆ�A�@�B�y�ё��u�ɂ��Ă͂P�䕪���͂P��ƂɁA�H��A���y�є��i�ɂ��Ă͂P�A�P�g����1���낢���Ƃɔ��肵�܂��B 1.�T�v �@������Ǝ҂ɊY������@�l���͔_�Ƌ����g�����ŐF�\�������o����@�l���A�����P�T�N�S���P�����畽���Q�O�N�R���R�P���܂ł̊ԂɂR�O���~�����̌������p���Y���擾���Ď��Ƃ̗p�ɋ������ꍇ�ɂ́A�����o���ɂ�葦�������Z����F�߂���̂ł��B�P�䂪�R�O���~�����Ȃ�A����w�����Ă��K�p�Ώۂł����B �@�����ɂ��A�����P�W�N�S���P���Ȍ�擾���̂��̂���́A�擾���z�̍��v�z���A�P���ƔN�x�ɂ��R�O�O���~�����x�ƂȂ�܂����B�R�O�O���~���镔���ɌW�錸�����p���Y�͓K�p�ΏۊO�ƂȂ�܂��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B 2.�K�p�Ώۖ@�l �@���̓���̑ΏۂƂȂ�@�l�́A�F�\���@�l�ł��钆����ƎҖ��͔_�Ƌ����g�����Ɍ����܂��B �i���j������Ǝ҂Ƃ́A���Ɍf����@�l�������܂��B �@�C �@���{���̊z���͏o�����̊z���P���~�ȉ��̖@�l �@�������A����̑�K�͖@�l�i���{���̊z�Ⴕ���͏o�����̊z���P���~����@�l���͎��{�Ⴕ���͏o����L���Ȃ��@�l�̂����A�펞�g�p����]�ƈ��̐���1,000�l����@�l�������A������Ɠ����琬������Ђ������܂��B�j�ɔ��s�ϊ������͏o���̑������͑��z�̂Q���̂P�ȏ�����L����Ă���@�l�y�тQ�ȏ�̑�K�͖@�l�ɔ��s�ϊ������͏o���̑������͑��z�̂R���̂Q�ȏ�����L����Ă���@�l�������܂��B �@�� �@���{���͏o����L���Ȃ��@�l�̂����A�펞�g�p����]�ƈ��̐���1,000�l�ȉ��̖@�l 3.�K�p�v���� �@�K�p���邽�߂ɂ́A�m��\�������ɏ��z�������p���Y�̎擾���z�Ɋւ��閾����Y�t���Đ\�����邱�Ƃ��K�v�Ƃ���Ă��܂��B 1.�T�v �@�擾���z���Q�O���~�����̌������p���Y�ɂ��ẮA���ƔN�x���ƂɁA�ꊇ���ĂR�N�Ԃŏ��p�ł�����@��I�����邱�Ƃ��ł��܂��B 2.�Ώێ��Y �@�擾���z���Q�O���~�����̌������p���Y���ΏۂƂȂ�܂��B �@�Ȃ��A�@�l�����Ƃ̗p�ɋ������擾���z�Q�O���~�����̌������p���Y�̂����A�ǂ̌������p���Y�����ꊇ���p�̑Ώۂɂ��邩�́A�@�l�̔C�ӂƂ���Ă��܂��B �@�܂��A�擾���z���P�O���~�����̌������p���Y�ł��A���������Z���̑ΏۂƂ����ɁA�ꊇ���p�̑ΏۂƂ��邱�Ƃ��ł��܂��B 3.�����Z���z �@�Ώێ��Y�����Ƃ̗p�ɋ��������ƔN�x�Ȍ�̑����Z���z�͎��̎Z���ɂ��܂��B 4.�K�p���� �@�ꊇ���p���Y�����Ƃ̗p�ɋ��������̑����鎖�ƔN�x�̊m��\�����Ɉꊇ���p���Y�ɌW��ꊇ���p�Ώۊz�̋L�ڂ�����܁A���A���̌v�Z�Ɋւ��鏑�ނ�ۑ����Ă���ꍇ�Ɍ���K�p����܂��B�܂��A�����Z���������z�̌v�Z�Ɋւ��閾��(�ʕ\�\�Z(�Z))���m��\�����ɓY�t����K�v������܂��B ���ݗ��Ƃ��đ����ƔF�߂�����̂͏]�ƈ��̎G�����ɊY�����܂��B �@�܂��A���̒��ߎx�������ŏ]�ƈ������p�Ɏg�p�����ꍇ�ȂǁA���ݗ��Ƃ��đ����ƔF�߂��Ȃ����̂́A�]�ƈ��Ƃ����n�ʂɊ�Â����ʗ��v�Ƃ��āA���^�����ɊY�����܂�(�������K�v)�B �@�Ȃ��A���s�������тɊ�Â����A���P�ʒ�z���Œ��ݎ،_���������Ă���ꍇ�Ȃǂͤ���̒��ݗ��͔�ېłƂȂ闷��̎���ٍςƂ͂������A�]�ƈ������̏��L����ԗ�����݂��Ă��邱��������ݗ��Ƃ��đ����ƔF�߂�����͎̂G�����ɁA���ݗ��Ƃ��đ����ƔF�߂Ȃ�Ȃ����̂͋��^�����ɊY�����܂��B �@�G�����ɊY������ꍇ�ł����Ă��A���̎x������]�ƈ��̋��^���̋��z��2,000���~�ȉ��Ŏ��̗v���̂����ꂩ�����Ίm��\���͕s�v�Ƃ���Ă��܂��B �@��̋��^�̎x������҂̂��̑��̏������z���Q�O���~�ȉ��ł���ꍇ �A�j�ȏ�̋��^�̎x������҂̏]���鋋�^�Ƃ̂��̑��̏����̍��v���z���Q�O���~�ȉ��ł���ꍇ �ٌ�m��p�̑����Z������ �@��ƌo�c�ɂ�����@���g���u���ɔ����A�ٌ�m�ƌږ�_������Ԋ�Ƃ����Ȃ�����܂���B�����ł́A�@�l���x�����ٌ�m��p�̑����Z�������ɂ��Ă��Љ�܂��B �P.���X�Ɏx�����ږ◿ �@�x���������܂ގ��ƔN�x�ő����Z������܂��B�Ȃ��A�ٌ�m�ɑ���ږ◿�͓���̃T�[�r�X����Ή��ł��̂ŁA�P�N����O���������Ƃ��Ă��Z���O����p�̎戵���͂ł��܂���B �Q.�i�ׂ̒���� �@������͑i���ʂɊւ�炸�x��������̂ł��̂ŁA���̎x�������܂ގ��ƔN�x�ő����Z������܂��B �R.������V �@�ٌ�m�Ƃ̌_���A���̂��ׂĂ̏����������ƂƂȂ��������܂ގ��ƔN�x�ő����ɎZ������܂��B �@�����������Ă��� �A��̓I���t�����ƂȂ鎖�����������Ă��� �B���z����̓I�ɎZ��ł��� �Œ莑�Y�̏��n�̎��� �@�������A�[�Ŏ҂̑I���ɂ��A���̎��Y�̏��n�_��̌��͔������ɂ�邱�Ƃ��F�߂��Ă��܂��B �@������̃P�[�X�ł́A�����I�戵���Ƃ��ĕ����P�X�N���̏��n�����Ƃ��Đ\�����Ă��ǂ��ł����A�����P�W�N���̏��n�����Ƃ��Đ\�����邱�Ƃ��o����Ƃ������ƂƂȂ�܂��B |
|
| �Ŗ������[�ꗗ | |
| �@ | |
�@